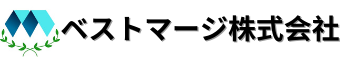エンジニアの業務をスムーズにこなすためには整理することが必要不可欠です。
紙の資料やPC上のファイルは当然として、
資料作成やプログラミングもその内容は整理されているべきです。
現在のタスクや人員の作業状況なんかも、
整理して確認するべきものと言えるでしょう。
今回はなんとなく気を付けるべきとは思っている「整理」について、
どのように考えて行うべきかを言語化してみました。
3つのポイントにまとめましたので、次の作業から意識してみてください。
①目的を意識する
整理は目的を持って行われます。
その多くは、誰かが作業をしやすくするためです。
フォルダ整理は、自分がファイルを探しやすくするため、
プログラムのコードは、自他共に理解しやすくするために整理されるべきということです。
もしこの目的意識が無いと、
自分のメモをどこに保存すべきかを人に聞いて困惑されたり、
自分流ソースコードを書いて意味不明な暗号を作り出したりしてしまいかねません。
「誰が」「何をするために」「どうするべきか」
これを考えるとどのように整理すべきかが自ずと見えてくるはずです。
②負荷の最小化を目指す
ファイルサーバから特定のファイルを探す、
資料の内容から欲しい情報を探す、
ソースコードから改修対象の処理を探す、etc…
探すという作業には労力がかかります。
その負荷を少しでも小さくする工夫をしようというのが2つ目のポイントです。
資料に目次を付けたり結論から述べたりすることは
読み手が全体像や流れを掴む手助けになりますし、
フォルダ分けやVisualStudioのコード折り畳み機能は
不要な情報を見せず探しやすくしてくれます。
命名規則やグラフ等の可視化なんかも負荷軽減のテクニックの1つと言えるでしょう。
ただしガイドの付け過ぎやフォルダの切り過ぎは
判断回数を増やすこととなり逆に労力が増えてしまいます。
整理自体の負荷も加味しつつ、バランスの良い状態を目指したいですね。
③整理の継続性
どれだけ気合いを入れて整理をしても、
それを継続出来なければ意味がありません。
整理のしやすさを追求するのが3つ目のポイントです。
もちろんただ楽をすれば良いという話ではなく、
管理のし過ぎを避けるという意味合いです。
特にチームで扱う資材を整理する場合は、
なるだけ万人が徹底出来る方法を取るべきでしょう。
また、例外が発生しにくい方法を取ることも大事で、
テキスト内だけだからとファイル名の使用禁止文字を命名規則として多用したり、
後先を考えずにナンバリングしたフォルダ名を付けたりすると、
後から事情が変わり整理し直しとなると大変です。
みんなが扱いやすく変化も受け入れやすい、
そんな風に整理が出来ると言うこと無しです。
まとめ
何となく理解して困っていないことでも、
あえて言語化してみると様々な気付きがあるものです。
皆さんも無意識の部分に目を向けて、
頭の中を整理してみてはいかがでしょうか?